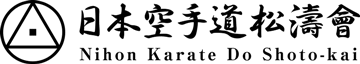立ち方
型の中にいろいろな姿勢がある。それを立ち方として整理説明する。
八字立
 八字立
八字立両脚を軽く開き-肩幅の程度-足先を正面に開いた、ごく普通の立ち方で、自然体ともいう。
この立ち方がすべての立ち方の基本でもある。手足はもちろん、膝、腰、腹、肩、どこも力まないように留意する。
閉足立
 閉足立
閉足立自然体から、静かに両足を閉じた姿。
騎馬立
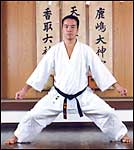
騎馬立(正面)

騎馬立(側面)
足を大きく開き、膝を足の親指の方向へ曲げる。重心は体の中心から真下に落とすようにする。
四股立
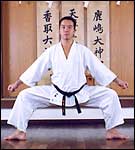
四股立(正面)

四股立(側面)
騎馬立の時と同じ足幅で、足先の方向が完全に真横に向くように心掛ける。
背筋は真っ直ぐに、腹を出して、思いきり膝を曲げて姿勢を落とすように注意する。
後屈立
 後屈立
後屈立膝を曲げるのと同時に、片足を軽く前に出し、支え足の膝は思いきり曲げる。重心は後ろ足に掛ける。
上体は真っ直ぐに、腹を突き出すようにして、充分に腰を落とす。
猫足立
 猫足立
猫足立自然体から、心持ち体をひねって、相手に向かって半身に対するように足の位置を変え、姿勢を低くした形。あるいは後屈立の前足を充分に引きつけた姿である。重心は後ろ足に掛ける。
前屈立
 前屈立
前屈立前膝を思いきり曲げ、後ろ足はやや内側に曲がるにまかせる。
上体は真っ直ぐ、重心は思いきり前足に近いところに置く。
不動立
 不動立
不動立前屈立の姿で、後ろ足の膝を心持ち曲げ、腹を思いきり出して、重心を真ん中に落とすようにする。
攻め方
空手を闘争の技術として考える場合、その技を「攻め」と「受け」に大別することが出来る。一般的に、攻め方としては、なぐる・蹴る・打つ・突く・つかむ等があるが、空手では突く・蹴るという練習が主体である。
初心者は突き・蹴りの技法を、みっちり身につけることが大切である。
蹴り
空手の「蹴り」には前蹴り・横蹴り・回し蹴り・三日月蹴り・二段蹴りなどがあるが、前蹴り・横蹴りを取り上げる。
なお、蹴る位置によって上段・中段・下段とある。
前蹴り
前蹴りの練習は、普通前屈の姿勢から行う。
前蹴りで特に大事なことは、蹴り足の膝を充分に曲げて、腿が腹に当たるところまで持ち上げる、つまり「抱え込む」ことである。

前屈立

充分抱え込む

前方を蹴る

引きながら
再び抱え込む
横蹴り
横蹴りには「蹴上げ」と「蹴込み(蹴放しともいう)」がある。
横蹴りは、普通騎馬立の姿勢から練習するが、習熟してきたら八字立・前屈立・後屈立から訓練してみることも必要である。

騎馬立

左足を出し

抱え込む

蹴込む
八字立からの前蹴り・横蹴り
参考に、八字立からの前蹴り・横蹴りを示す。

八字立

前蹴り

八字立

横蹴り
突き
松濤會の拳は、普通誰でもがやるような拳で、ただ親指と小指をしっかりしめて中指の第二関節が相手に当たるようにする。ただ、拳を握る時に、変に肘や肩にまで力が入らないように注意する。
突きの練習として、八字立・騎馬立での突き、前屈立から前進して追突き・逆突きがある。拳に力を集中して、「突き通す」気持ちで突くことが大事である。
正拳の握り方




騎馬立の突き・追突きの分解動作
騎馬立の突き・追突きの分解動作を示す。
騎馬立ちの突きの分解動作
脇と肩に必要以上の力を入れない。


追突きの分解動作
脇と肩に必要以上の力を入れない。



受け
基本稽古の中では、突き・受けと区別して練習しているが、受け技は、単純に、受けるだけの技ではなく、そのままの姿、形で攻撃に転ずるものである。
一般的に、受け技として下段払い・上段揚受け・手刀受け・腕受け・鉄槌打ち受け等がある。ここでは、下段払い・上段揚受け・手刀受けについて示す。
下段払い
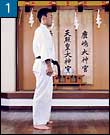

形としては、払う方の手の反対側の肩上から斜めに、手と同じ側の膝上十五、六センチの所へ払い落とす。
八字立からの下段払いの分解動作を示す。
上段揚受け


基本的な意味としては、上段を突いてくる手を払い上げることである。受ける手を反対側の腰から引手と交差させながら揚受けをすることが重要である。
八字立からの上段揚受け分解動作を示す。
手刀受け
大変難しい受け技である。
八字立から、膝を曲げて、体を落としつつ、右足一本で体重を支えるようにして、左足を前に出す。この時、前足には出来るだけ体重がかからないように、軽く出す。 この足を動かすのと同時に、左手の手を開き(指先をそろえて伸ばす)、右手を軽く出し、左手を右肩の前に、掌を上にして持って行き、そこから、左右両手をひきしぼるようにして、右手は肘を脇につけるようにして、手は掌を上にしてみぞおちの前あたりに止める。 左手は、突いてくる腕を切るように、右肩先から斜めに左へ出す。ただ切るだけでなく、相手の手を引っかけるという意味を加えることが大切である。
八字立からの手刀受けの分解動作を示す。